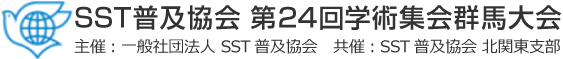サテライト企画Satellite研修会Workshop
大会前日の12月6日(金)14:00~『研修会』を開催いたします。
申込期間 7月29日(月)〜11月29日(金)(定員になりしだい終了)
『研修会』の内容は、以下のとおりです。
1. 被災当事者支援のSST
災害時にはさまざまな困難事が想定されますが、日頃からSSTを学び実践しておくことで、その程度を減弱させることができますし、周囲と協力し合い、うまく乗り越えられた場合には、回復を促進する力にもなります。どのようなSSTを日頃から学習しておくとよいか、みんなで考えるセッションです。
DPAT事務局の福生泰久先生から、日頃の活動につきお話していただき、その後、片柳光昭先生(みやぎ心のケアセンター)の企画で、当事者が災害被災時に必要となる10のスキルについて学ぶ、日頃のSST活動で、10のスキルを身につける方法を体験する、などをテーマにワークを行います。
【タイムスケジュール】
1 講義(14:00~15:00) 講師 福生泰久先生(DPAT事務局・神奈川県立精神医療センター)
DPAT事務局の活動状況について
2 演習(15:10~17:00) 担当 片柳光昭先生(みやぎ心のケアセンター)
当事者が災害被災時に必要となる10のスキルについて
日頃のSSTの取り組みの中で、必要なスキルを身につける方法について
【紹介文】
近年、我が国においては大規模かつ重大な被害をもたらす自然災害が頻回に発生しており、統合失調症を抱える
当事者(以下、被災当事者)の被災後の生活においても、重大な影響が及ぶことは想像に難くありません。
本企画では、DPATの活動状況の講義と、AMED-SST第4領域の研究で明らかになった自然災害の被災後の生活に
特に重要と考えられる10のスキルを紹介した後、それらのスキルを身につけるための方法を演習形式で学びます。
災害後の生活に備えるためのSSTに取り組みたいと考えている方、災害時における支援活動の中で
SSTを用いた関わりを学びたいと考えている方、災害後の被災当事者への生活支援に関心のある方等に
是非受講して頂き、日頃の支援に本企画の内容を加えて頂ければ幸いです。
2. 依存症者回復支援のSST
薬物依存症の回復支援に尽力していただいている人たちに、SSTを活用していただき、対象となる人たちの社会復帰を促進することを目的としたセッションです。
神奈川県立精神医療センターの小林桜児先生から、薬物依存症の現状と課題につきお話しいただき、その後、浅見隆康先生(群馬大学健康支援総合センター)の企画で、依存症者が薬物乱用を繰り返す理由は、長年にわたり身につけてきた生活行動にある、SSTは生活行動の変容を促す、生活行動の変容のための具体的な方法を学ぶ、などをテーマにワークを行います。
【タイムスケジュール】
1 講義(14:00~15:00) 講師 小林桜児先生(神奈川県立精神医療センター)
薬物依存症の現状と課題について
2 演習(15:10~17:00) 担当 浅見隆康先生(群馬大学健康支援総合センター)
長年にわたる生活行動が、薬物使用を繰り返す理由の一つ
生活行動を変えるSSTを学び、支援に役立てる
【紹介文】
覚せい剤を繰り返し使用する理由に、「退屈だから」、「ただ何となく」といったものが挙げられます。
薬物依存症者が抱える虚無、孤立、孤独といった課題がみられます。
この方々の、それでも何とかしたい気持ちを引き出し、その気持ちを強めていく方法を学びます。
SSTやソリューション・フォーカスト・アプローチなどを用い、演習を行います。
たとえば、
・ある日のことです。その対象者の問題が全くなくなっています。それはどのようなことから気づきますか。
・訪問したある日のことです。対象者の様子がいつもと違うことに気づきました。
など、参加者に質問しみんなで回復支援の方法を考えていきます。
そして最後に、「相手の話に耳を傾けるスキル」を二人1組になって行います。
地域で回復支援の輪を広げましょう。
3. 働く場での健康対策―SSTを活用する取り組み―
企業の場でのメンタルヘルス対策にSSTが活用されています。その一端を紹介し、働く人たちの健康増進に役立つSSTを考えるセッションです。
労働衛生コンサルトの藤田晴康先生(赤城病院内科)から、働く場での健康対策の現状と課題につきお話しいただき、その後、今村弥生先生(杏林大学医学部)の企画で、企業の場でSSTを取り入れたコミュニケーション作りを紹介する、職員の教育にSSTの導入の仕方を考える、などをテーマにワークを行います。
【タイムスケジュール】
1 講義(14:00~15:00) 講師 藤田晴康先生(労働衛生コンサルタント、赤城病院内科)
働く場での健康対策の現状と課題
2 演習(15:10~17:00) 担当 今村弥生先生(杏林大学医学部精神科)
コミュニケーション作りに役立つSSTを知る
職場にSSTの導入の仕方を考える
【紹介文】
働く人にとってのメンタルヘルスについて、産業医の視点から概論の講義の後、実際の支援にSSTを応用するため、
デモンストレーション・参加者グループによる実技を行うワークショップです。
練習用に、産業メンタルヘルスの現場でよくある事例を用意しますが、
相談したい事例・場面をもとに練習することも念頭に入れています。
4. 学校の場での発達障害児・者支援―SSTを活用する取り組み―
SST関係者が教育現場に出向き、発達障害児・者支援として、SSTを活用した取り組みが行われています。その一端を紹介し、それぞれの場でどのようにSSTを活用できるか、アイデアが得られるセッションです。
石川県こころの健康センター・発達障害者支援センターの角田雅彦先生から、発達障害児・者の特性につきお話しいただき、その後、柴田貴美子先生(埼玉県立大学保健医療福祉学部作業療法学科)の企画で、教育の場でSSTを取り入れた支援の取り組みを紹介する、それぞれの場でSSTの活用の仕方を考える、などをテーマにワークを行います。
【タイムスケジュール】
1 講義(14:00~15:00) 講師 角田雅彦先生(石川県こころの健康センター・発達障害者支援センター)
発達障害の特性について
2 演習(15:10~17:00) 担当 柴田貴美子先生(埼玉県立大学保健医療福祉学部作業療法学科)
発達障害児とその親を対象とした 親子SSTプログラムの紹介
参加者の場でSSTの活用の仕方を考える
【紹介文】
この研修会では、まず角田雅彦先生(石川県こころの健康センター・発達障害者支援センター)より、
発達障害児・者の特性についての講義をしていただきます。
その後、発達障害児とその保護者を対象とした「親子SSTプログラム」を紹介し、
実践から得られた知見を報告します。
フロアの皆様とディスカッションし、発達障害児とその親の生活が豊かになるためのSSTの可能性を
検討できればと思っています。
5. 回復支援と自分を語る場
医療の場や地域で、当事者や家族が安心して語る場を作り、回復支援を進める方法を学ぶセッションです。
福岡大学名誉教授・六本松心理教育臨床オフィスの皿田洋子先生から、自分のことを安心して語る場の意義につきお話しいただき、その後、坂本 浩先生(兵庫医療大学リハビリテーション学部)の企画で、医療の場や地域で、当事者や家族支援に取り組んでいる様子を知る、参加者が、自分たちの医療や地域の場で、語る場の作り方を考える、などをテーマにワークを行います。
【タイムスケジュール】
1 講義(14:00~15:00) 講師 皿田洋子先生(福岡大学名誉教授・六本松心理教育臨床オフィス)
自分のことを安心して語る場の意義について
2 演習(15:10~17:00) 担当 坂本 浩先生(兵庫医療大学リハビリテーション学部)
医療の場や地域で、当事者や家族支援に取組む様子を知る
参加者が、自分たちの医療や地域の場で、語る場の作り方を考える
【紹介文】
今回の研修会では、まず皿田洋子先生(臨床心理士、SST普及協会認定講師、家族心理教育インストラクター、
六本松心理教育臨床オフィス)から「自分を語る意義」というテーマで講義をしていただきます。
そして、後半は会場をSSTのような形式に変え、当事者、当事者家族、ピアサポーター、オープンダイアローグ実践者、
就労支援実践者の5名の話題提供者と共に普段行っているSSTが、少しずつ自分を語ることができる場になっていくための
工夫や気づきについて語り合う場にしたいと考えています。
SST認定講師の吉田悦規先生(宝塚三田病院)に後半のスーパーバイザーをやっていただきます。
今回のワークを通して得た内容を日々のSSTで活用していただければ幸いです。
日時
2019年12月6日(金) 14:00~17:00(受付は13:30から)
会場
前橋テルサ(群馬県前橋市千代田町二丁目5番1号) 内
「被災当事者支援のSST」 けやきの間A(8階)
「依存症者回復支援のSST」 けやきの間B(8階)
「働く場での健康対策―SSTを活用する取り組み―」 つつじの間A(9階)
「学校の場での発達障害児・者支援―SSTを活用する取り組み―」 つつじの間B(9階)
「回復支援と自分を語る場」 赤城の間
定員
各50名
ただし、「回復支援と自分を語る場」は、30名となります。
参加費
3千円(当事者・家族・学生は2千円)
ただし、大会に参加登録された方は無料です。
お申込み方法
ホームページより、申込用紙をダウンロードし必要事項をご記入後、添付メールもしくはFAXでお申込みください。
確認事項(必ずご確認ください)
1)「参加申し込み書」をメール添付もしくはFAXしていただいた後に、「研修会参加申し込み確認書」又は「研修会参加確定書」を
お送りします。
定員に達した場合は、参加をお断りする場合もありますので、ご了承ください。
1週間以上過ぎても返信が無い場合は下記にご連絡ください。
2)学術集会に参加される方は、「学術集会事前申し込み確定書」と「研修会参加申し込み確定書」を印刷してご持参ください。
3)学術集会に参加されない方には、「研修会参加申し込み確認書」に記載されている銀行口座に参加費をお振込みください。
お振込みの際には、振り込み人氏名の前に「参加申し込み番号」を追加入力してください。
お振込みを確認後に、「研修会参加確定書」をお送りします。当日は「研修会参加確定書」を印刷してご持参ください。
4)振込期日は11月29日です。「研修会参加確定書」は遅くても12月4日頃までにお送りします。
期日を過ぎて返信がない場合は下記にご連絡ください。