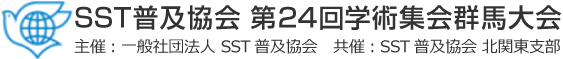大会概要About
日程・会場:
2019年12月7日(土)~8日(日)
第1日目 9:00 開会 第2日目 14:00 閉会
前橋テルサ(〒371-0022 群馬県前橋市千代田町二丁目5番1号)テーマ:
「メンタルプラスの時代へ もっとモバイルな、もっとカラフルなSSTを」大会関係者:
大会顧問 福田正人(群馬大学)
大会長 浅見隆康(群馬大学健康支援総合センター)
副大会長 赤田卓志朗(群馬県立精神医療センター)
実行委員長 須藤友博(群馬県立精神医療センター)プログラム
<内容>- ① 会長講演(大会1日目 9:10~10:00)
演者:丹羽真一先生(福島県立医科大学会津医療センター)
座長:福田正人先生(群馬大学)
テーマ:SSTを広げ深める
【紹介文】
5年先の2025年には普及協会が発足して30周年を迎え、協会が法人化して10周年を迎える。
日本でSSTを普及する上で協会が行なってきた事業と果たしてきた役割は大きなものだと実感される。
そういう節目の時期を迎えようとする今日、今後さらにSSTを普及するうえで協会はどんな事業を
進めることが必要だろうか? - ② 大会長講演(大会2日目 9:00~9:50)
講師:浅見隆康先生(群馬大学健康支援総合センター)
座長:皿田洋子先生(六本松心理教育臨床オフィス)
テーマ:家族とともにある支援
【紹介文】
家族とともにある支援を目指した「土曜学校」の意義を次のように考えています。
1 継続した家族支援
毎年6月から翌年の5月にかけ、年間計画を立て運用し、継続して教室が開催される。
2 家族と関係者の共同による運用
知識としての講義とグループワーク(GW)が行われる。
GWでは家族がリーダーを務め、土曜学校関係者が協力し、話し合いを進めていく。
話し合った内容をまとめ、土曜学校準備会にてワークの進め方を再検討し、SSTの取り入れ方などにつき振り返る。
3 家族による家族支援
年余にわたり参加している家族が新たに参加し始めた家族に対し、土曜学校終了後に助言やアドバイスを行っている。
4 土曜学校の変化
どのような内容にすると、家族のその気を育て、回復への道を歩み始めることができるか、参加家族の意見も取り入れ、
内容を腐心してきた。
いろいろな場でこのような支援の場を作ることが求められています。 - ③ 教育講演
教育講演 1(大会1日目 10:10~11:00)
講師:西園昌久先生(一般社団法人SST普及協会名誉会長)
座長:加瀬昭彦先生(横浜舞岡病院)
テーマ:自らを語る意味―SSTの真価
【紹介文】
SSTはアメリカ合衆国で開発された精神障害者に対する一種の集団精神療法である。
今では、広く、世界各地に普及しているが、アメリカ以外では、我が国の普及発展が著しい。
SSTは治療者とその補助者を中心に集まり、療養上のこと、日常生活上のこと、
さらには交友関係、家族関係、自分のあり方について発言し、集団の中でそのことが語り合われる。
一般に、孤独で不安で、しばしば被害的心性に災いされている障害者にとって、
受け入れられ、包まれ、評価される体験は最大の癒しとなり得る。
集団への不安や自らを語ることへの抵抗が薄れれば、「自らを語ること」は深化する。
それに応じる集団の受け入れ機能とそれを導く治療者の介入によって、
「自らを語ること」の内容はより現実適応的なものに進歩するであろう。
教育講演 2(大会1日目 11:10~12:00)
講師:前田ケイ先生(ルーテル学院大学)
座長:河岸光子先生(吉祥寺病院)
テーマ:SSTの基本―言葉でうまく伝えられなくても―
【紹介文】
言葉によらないコミュニケーション、
たとえば、身体言語(姿勢や身体の動きなど)と周辺言語(声の高さや話す速さなど)が適切に使われれば、
言葉より大きい効果をもつことは、私達自身の体験から、また、コミュニケーション研究からも知られています。
私達はこのような言葉によらない効果的なコミュニケーション行動をSSTのなかでどう教えたらいいでしょうか。
私が経験した8つの実例を、友人らの協力を得て、舞台の上で演じながら、説明してみます。
教育講演 3(大会1日目 17:10~18:00)
講師:池淵恵美先生(帝京平成大学大学院)
座長:後藤雅博先生(こころのクリニック ウィズ)
テーマ:人生の回復を支援する精神障害リハビリテーション
【紹介文】
こころの病から人はどのようにして回復していくのでしょうか。
リハビリテーションは歩行訓練というイメージがありますが、
もともとの意味は「社会における生活や権利の回復」です。
精神障害においては「生活の障害 disability」がまだ十分に明確になっておらず、スティグマもあります。
その中で「障害があってもなくても、その人なりの満足のゆく人生を生きられるようになることやそのプロセス」である
パーソナルリカバリーが注目されています。
症状軽減や社会生活の改善がなかったとしても、パーソナルリカバリーは起こりますが、客観的な改善があった方が
リカバリーにより役立つことがわかっています。
SSTは、学校や職場や仲間との交流など、ふだんの生活をめざしている人が
ぶつかる壁を乗り越える手がかりを提供する、有効な支援法です。
当日はこうしたパーソナルリカバリーと客観的な改善を支援する精神障害リハビリテーションについて
お話ししたいと思います。 - ④ シンポジウム(大会2日目 10:00~12:00)
テーマ:方法論の垣根を越えて、こころの健康づくりの新たな時代を招く
司会:須藤友博先生(群馬県立精神医療センター)
安西信雄先生(帝京平成大学大学院)
内容:病を抱える困難事を、家族や当事者はどう捉え、前向きに受け止められるのか、
家族や当事者からこれまでの道のりをご紹介いただき、その時々にどのような
支援が必要であったか、その中でどう取り組み、乗り越えてきたか、などを基に、
それぞれの立場から支援方法を紹介します。
シンポジスト:
・事例提供:家族教室「土曜学校」家族・当事者
・SST(社会生活技能訓練):佐藤珠江先生(埼玉精神神経センター)
・CBT(認知行動療法):小野樹郎先生(群馬大学)
・OD/AD(オープンダイアローグ):笹原信一朗先生(筑波大学)
岩波孝穂先生(順天堂大学) - ⑤ 一般演題発表(大会1日目 口演 13:30~16:50 / ポスター 13:30~16:30)
※口演形式、ポスター形式を募集
※口演(質疑応答を含め15分)、ポスター(質疑応答を含め10分) - ⑥ 自主企画(大会1日目 13:30~16:30・大会2日目 10:00~11:30)
※1企画は90分
※普及協会で公募し、採択は群馬大会運営委員会で行います。 - ⑦ 会員報告会(大会2日目 13:10~13:40)
- ⑧ 市民公開講座(大会2日目 14:20~16:00)
第一部 講演
テーマ:「居場所がほしい―不登校生だったボクの今」
講師:浅見直輝先生
第二部 対談
テーマ:「居場所をつくる」
対談者:浅見直輝先生
佐藤真人先生(アリスの広場)
司会:佐藤浩司先生(群馬県こころの健康センター)
吉田真弓先生(群馬県立安中総合学園高等学校)
共催:群馬大学・地域貢献事業 群馬県精神保健福祉協会 - ⑨ ご当地セミナー(大会2日目 12:10~13:00)
講演1
講師:小川一夫先生(中之条病院)
座長:天笠 崇先生(代々木病院)
テーマ:生活臨床とコ・プロダクション
【紹介文】
精神保健医療福祉の領域では今や、「生活」の視点は当り前となっているように見える。
しかし、生活のどこに着目しどのように働きかけようとしているのかは様々である。
生活臨床は、この生活概念を精神科医療に意図的に導入し、生活の中で病気を見立て生活の中で働きかけようとする
治療指針である。
それは、1958年に群馬大学病院精神科で始められた「統合失調症再発予防5ヶ年計画」の取組みを
通じて誕生したものであり、半世紀余りを経て今日に至っている。
生活臨床は、当事者の価値意識を反映した生活上の課題(指向する課題)に着目し、その達成支援に焦点を当てるが、
このプロセスでは、近年、支援のあり方として注目されるコ・プロダクション(共同創造)のアプローチと
共通するものが見出せる。
そこで、生活臨床とコ・プロダクションに共通して見られる特徴を明らかにし、その意義を考察してみたい。
講演2
講師:今井航平先生(群馬県こころの健康センター)
座長:橋本俊英先生(上毛病院)
テーマ:依存症者の家族支援
【紹介文】
アルコールや薬物、ギャンブルなどによる依存症において、家族支援は、家族自身の困難や苦労を減らすため、
また、依存症者本人の回復のためにも重要なものである。
群馬県こころの健康センターでは、2013年より依存症家族教室(月1回)において
『ぐんま依存症ファミリートレーニング(GIFT)』を実施している。
これは、CRAFTをベースに作成した集団CBTプログラムである。
CRAFTは、家族が本人への対応の仕方を学び、積極的に関わることを通して、
依存症の改善や家族の苦労軽減を達成するためのプログラムである。
演者がつくづく思うのは「頭で理解することと身体で覚えることは違う」
「知識を取り入れて生活を変えるためにはトレーニングが必要」ということである。
本セッションでは依存症家族支援について概説しつつ、皆さんの日々の生活や仕事に役立つ知識やスキルを
ぐんま土産として持ち帰って頂けるよう、処理・送信予定である。
講演3
講師:田川みなみ先生(群馬県立精神医療センター)
座長:岩田和彦先生(大阪医療センター)
テーマ:脳画像と精神医学
【紹介文】
脳は、様々な情報や指令をやりとりする神経のネットワークと言えます。
この、神経ネットワークの概念は、人工知能の開発にも応用されています。
では、人工知能がこのまま進化していけば、人間の脳と同じものになるのでしょうか?
現時点では、人の脳と人工知能には大きな違いがあります。その一つが、安静時脳活動です。
人工知能は、与えられた学習課題や刺激に対し、時には人の脳以上に正確に素早く反応します。
しかし、生き物の脳というのは課題や刺激がなくても、一定のパターンで活動していることが知られています。
この活動は自発的脳活動とも言われ、人の社会的な活動や、精神疾患とも深く関わっていると言われていますが、
はっきりとしたことはまだ解明されていません。
当日は脳磁図を用いた安静時脳活動の研究について、これらの話を交えながら発表したいと思います。
- ⑫ 懇親会(大会1日目 18:20~20:00)
会場はけやきの間 - ⑬ 研修会(大会前日 14:00~17:00 詳細は別紙)
- ⑭ 支部交流会(大会1日目 16:00~17:00)
司会:執行委員会事務局、北関東支部事務局長
執行委員会と協力し、支部交流会を行い、支部活動の活性化につき検討します。 - ⑮ 新社員総会(大会前日 17:00~20:00)
会場は尾瀬の間 - ⑯ 当事者の声
賛助会員施設でSSTを学ぶ当事者から、「あったらいいな、こんなこと。できたらいいな、そんなこと。」をテーマに
アイデアを公募し、ポスターセッションの一部で発表会を行い、参加者の投票により上位3位を決め、表彰します。
詳細はこちらへ - ⑰ WRAP(大会2日目 13:10~14:10)
講師:増川ねてる先生
進行:高山千恵美先生
【紹介文】
WRAP®は、「Wellness Recovery Action Plan」の頭文字をとったもので、
日本語では「元気回復行動プラン」と訳されています。
本としてまとめられたのがアメリカで、1997年(初版、改訂版2002年)、
日本語訳が出たのが2009年(オフィス道具箱)。
2010年にはSAMHSA(Substance Abuse and Mental Health Services Administration)による
EBP(Evidence Based Practices)の認定を受けており、
アメリカ50州はもちろん、世界各国における実践があります。
WRAPは、精神科の治療薬が上手く使えなくなった時、
メアリーエレン・コープランドさんが行った1989年の調査から始まります。
《実際に“リカバリー“している人たちってどんな人なの?》
そこからリカバリーしていた人たちの共通点(リカバリーのキーコンセプト)が明らかになります。
やがて、その知恵を実生活に取り入れる仕組みとして「WRAP」が開発されました。
筆者は、2006年に通っていた施設でWRAPに出会い、仲間たちと試行錯誤してWRAPを作り、
使うようになりました。
体験談を合わせて、WRAPのご紹介をしたいと思います。 - ⑱ ランチョンセミナー(大会1日目 12:10~13:10)
 演題:「いろいろな人達と連携し,ともに働く-多職種チームの作り方と運用のポイント-」
演題:「いろいろな人達と連携し,ともに働く-多職種チームの作り方と運用のポイント-」
講師:渡邉博幸先生(千葉大学社会精神保健教育研究センター特任教授/学而会木村病院院長)
【紹介文】
精神科の支援サービスの現場では、異なる職場ではたらく、いろいろな職種の人たちが連携して、
当事者・家族への様々な希望に応えていくことが標準になりつつあります。
しかし、どのような連携システムが有益かについては十分な結論は出ていません。
このセミナーでは、千葉市にある都市型の単科精神科病院での最近の取り組みを例に、
1)救急入院治療の場面、
2)産後メンタルケアの場面、
3)就労支援の場面
での、多職種チームの作り方と運用の実際をご紹介します。
また、保健医療福祉の専門家だけでなく、会社や身近な地域の人々、そして当事者の方々とともにアイデアを出し合い、
企画し、実践するゆるやかな連携協働も試みています。
多職種連携が当たり前に実践される時代に並行して、当事者・支援者の垣根を超えた
『関係者連携・協働』も花開きつつあることを確かに実感しています。
時間に限りがありますが、そのことについても触れてみたいと思います。
- ① 会長講演(大会1日目 9:10~10:00)
公募演題募集:
2019年8月19日(月)~10月18日(金)日本精神神経学会 精神科専門医単位について
(社)日本精神神経学会の専門医単位制度における専門医資格更新のための
ポイント取得対象の学会の指定を受けています。
ポイント受付は総合受付にて行います。日本作業療法士協会 生涯教育制度について
基礎ポイント対象学会となっています。
作業療法士の参加者は参加証明書を総合受付で受け取ってください。参加登録
学会参加費
区分 事前登録参加 当日参加 SST普及協会会員 5,000円 6,000円 非会員 6,000円 7,000円 当事者・家族・学生 2,000円 懇親会 5,000円 ※会員に関するお知らせ:賛助会員につきましては、1施設につき6人までを会員扱いとします。
連絡先
SST普及協会 第24回学術集会群馬大会 運営事務局
(株)トリョウビジネスサービス内
〒104-0045 東京都中央区築地2-3-4-9F
Tel:03-3547-9664
Fax:03-3547-9684